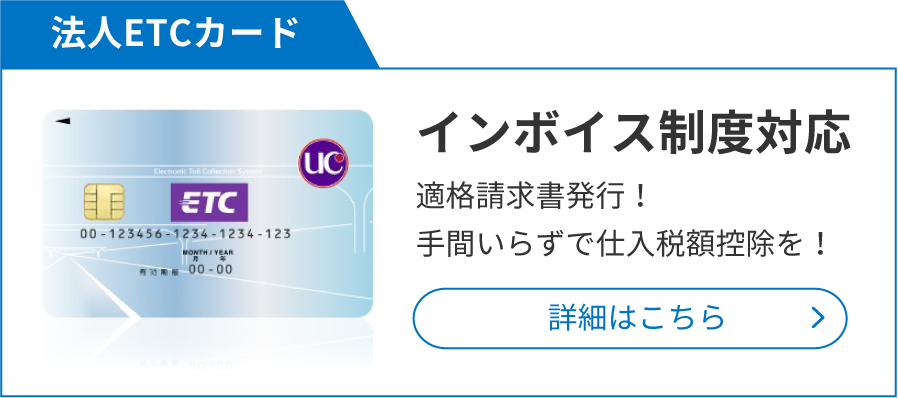【価格高騰】ガソリンの値上がりいつまで続く!?緩和補助金の廃止で負担はどう変わるのか
2025/03/27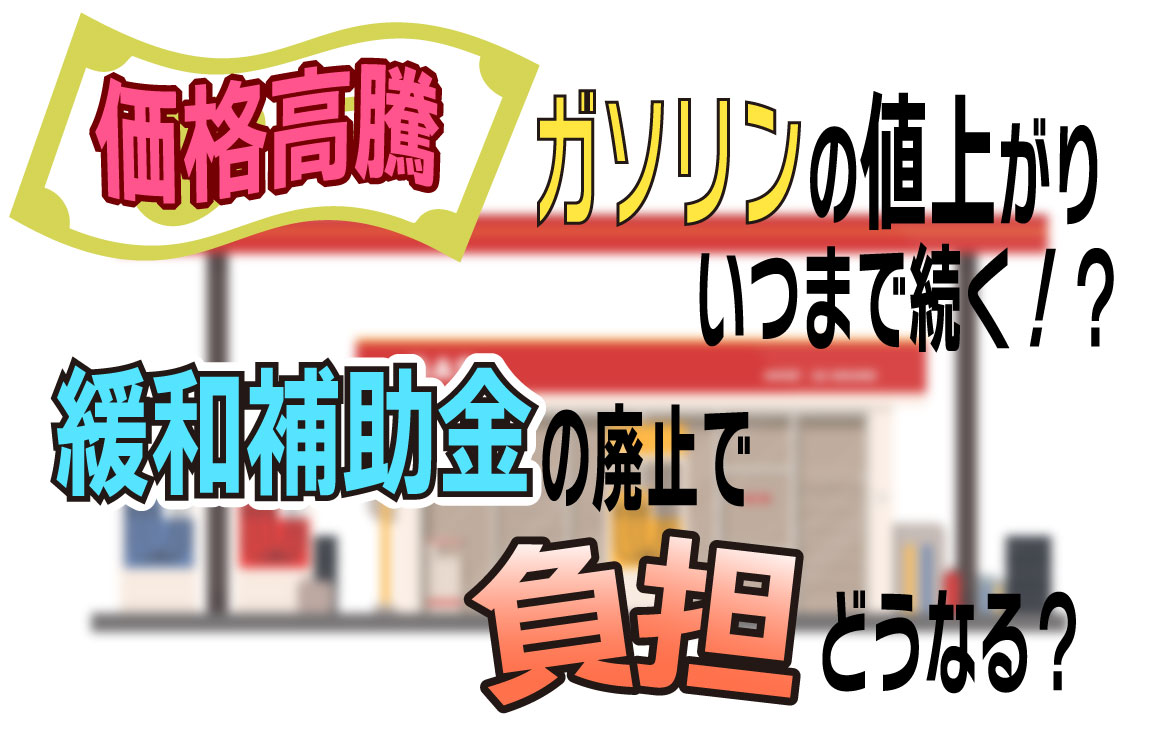
2024年末より高騰が続いているガソリン価格。なかなか下がらない価格について悩まれている方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、ガソリン価格高騰について
・どのような理由があるのか
・ガソリン価格の詳細
・税金・補助金について
の3点についてわかりやすく解説していきます。
また、個人でできる価格高騰への対策についても併せてご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。
ガソリン高騰の原因
 我々消費者の家計に直結するガソリン価格の高騰ですが、いったいなぜここまで高騰しているのでしょうか。
我々消費者の家計に直結するガソリン価格の高騰ですが、いったいなぜここまで高騰しているのでしょうか。
資源エネルギー庁が公表している全国平均ガソリン価格の推移をみると、2025年1月の価格は180.7円で、2022年1月の170.2円と比較すると10.5円ほど価格が高騰していることがわかります。
▼最新の資源エネルギー庁公表ガソリン価格はこちら
調査の結果|石油製品価格調査|資源エネルギー庁
ガソリン価格が高騰するのはどうしてなのでしょうか。主な原因は3つあります。
・円安の影響
・原油需要の増加
・産油地域の治安悪化や自然災害
それぞれ詳しく見ていきましょう。
円安による影響
日本の原油自給率は1970年頃から2021年度に至るまで継続して0.5%未満の水準にあります。資源エネルギーの大部分を海外に依存しているため、円安の影響を大きく受け、ガソリン価格にも直結しています。
原油需要の増加
コロナ禍が明けたことにより、世界的に景気が回復していく中で原油に対する需要が高まっています。また、OPEC(石油輸出機構)が減産を発表したことによって供給が減少しているため、より価格の高騰が進行しています。
産油地での治安の悪化、自然災害
原油の輸入元、と聞くとサウジアラビアなどの中東地域を思い浮かべる方が多いでしょう。実際に主な輸入元は中東地域ですが、そのほかにも中国・ロシア・中東アジアからも輸入をしています。これに含まれるロシアが、2022年からウクライナ侵攻を始めたことにより、該当地域への制裁として輸出が禁じられることがありました。ウクライナ侵攻を遠い国の出来事のように感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、我々の生活に直接的な影響をもたらしています。
先述した通り日本の原油輸入割合は99.5%ですが、その約90%を中東地域からの輸入が占めています。1973年と1979年の過去2度の石油危機の経験から、諸外国と比較しても高い水準である中東依存度を懸念して輸入先の多角化を図りました。しかし、コロナ感染症の流行による流通の停滞や、戦争や紛争に伴う輸出国からの原油輸出量減少などの影響により、中東依存度は2021年度に92.5%まで増大しました。
また、多くの自然災害などにより原油輸出国内で需要が増加したことで、輸入価格の高騰が避けられない状況となっています。
コロナ禍からの経済回復を図る補助金
燃料油価格の高騰はほぼすべての物価の高騰になりうるものです。それがコロナ禍からの経済回復の重荷となることを防ぐために、政府は価格抑制を目的とした緩和措置を講じています。
2022年4月25日時点では、全国平均価格が170円/L以上になった場合、1Lあたり上限35円を燃料油元売りに補助金支給していました。
補助金の効果は以下のサイトの通りで、価格高騰を抑制できていると言えるでしょう。
補助金の減額
その補助金も徐々に減少し、2025年1月16日からは補助率0%となっています。
状況を見定めて185円を上回る価格に対する補助率を段階的に見直す予定のようですが、2024年末のガソリン価格の上り幅は大きく感じた方も多いのではないでしょうか。2024年11月頃165~170円/Lだった価格が、2024年12月頃175~180円/Lとなり、補助がなくなった現在2024年2月は、全国平均約185円/Lとなっています。
ガソリン減税
そもそも、ガソリンの価格は「ガソリン本体+石油税+ガソリン税+消費税」の4つで価格が設定されています。
3つ目に記載したガソリン税は、「揮発油税+地方揮発油税」を合わせた総称で53.8円/L課せられ、道路整備の財源を補う名目でこのうち25.1円/Lが暫定税率として本来の税額に上乗せされている状況です。
レギュラーガソリンが180円/Lのとき、内訳はガソリン価格107.4円/L、ガソリン税53.8円/L、石油税2.8円/L、これら合計164円に消費税10%の16円となっています。
2024年12月11日に上記の「暫定税率」の廃止が明記されましたが、その時期については明言されていません。
燃費をよくするためには
少しでもガソリンを節約するために、燃費の良い走行について4つコツをご紹介いたします。
3つの急をしない
「3つの急」という言葉を聞いたことがありますか。「急停車」「急発進」「急ハンドル」のことを指します。
これらは事故につながることはもちろん、エンジンに負荷がかかってしまい燃費が悪くなる一因となります。特に「急発進」は最もガソリンを使用するので回数を減らすように心がけましょう。
車体の重さ
燃費の良さと、車重は反比例の関係にあります。不要な荷物は載せずに軽量化を図ることで燃費の向上につながる可能性があります。
タイヤの空気圧
ご使用中の車のタイヤ空気圧は適正でしょうか。
JAFが公表している「タイヤの空気圧と燃費の関係性についての実験」によると、1年間に15,000km走行し、燃料価格が185円の場合、年間でかかるガソリン代は次のようになります。
適正値:213,490円 空気圧30%減:223,850円(適正値+10,360円)
空気圧60%減:243,460円(適正値+29,970円)
空気圧は見た目から変化に気が付くこともできるかと思います。燃料費が高騰している今、走行前に確認してみてはいかがでしょうか。
停車時間・回数
車は加減速を繰り返すとエンジンに大きな負荷がかかってしまうことをご存知でしたか。一般道では信号や踏切、横断歩道などで停車することが多いでしょう。車種や車体の大きさによって異なりますが、普通自動車は60~80Km/hの速度が燃費良く走れるようにセッティングされています。
また、走行中最も燃費が悪くなってしまうのは何度も「発進」のタイミングがあることですので、加減速に加え停車回数が少ない方がより燃費良く走行できるでしょう。
高速道路の利用
ガソリンをお得に
各ガソリンスタンドで会員登録をするとお得に割引を受けられることもあります。ガソリンカードを利用するなど、少しでもお得にガソリンをいれられるか、お近くのスタンドに確認してみるのも良いでしょう。
▼当組合では、組合員様向けにAMSカード(ガソリンカード)も発行をしております。
ETCカード
当組合では、高速道路をお得にご利用できる法人様/個人事業主様向けETCカードの発行を行っています。停車や加減速が少ない高速道路をお得にご利用してみませんか。
詳細、資料請求はこちらからお気軽にお申し付けください。
最後に
物価高騰のあおりが特に感じられるガソリン価格。かしこく工夫して少しでもお得にガソリンを利用していきましょう。